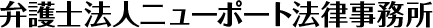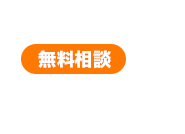非嫡出子や前妻との子の相続分はどうなるか?

法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことを「嫡出子」といいます。今回は、被相続人の死亡時に、死亡時の配偶者ともうけた嫡出子だけでなく、別の女性と婚外でもうけた非嫡出子や前妻ともうけた嫡出子がいたとき、それらの子の相続分はどうなるかについてご説明いたします。
相続人の範囲
民法は、相続人の範囲を明確に規定しています。被相続人に配偶者がいるときは、配偶者が必ず相続人となり、被相続人に子がいるときは、子が第1順位の相続人となります。したがって、嫡出子・非嫡出子の別にかかわらず、被相続人に子がいるときは、配偶者とともに相続人となって遺産分割に関与することになります。このときの法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子同士の法定相続分
被相続人に配偶者と子がいるときは、相続財産のうち、2分の1を配偶者が相続し、残りの2分の1を子が相続することになります。では、子が複数いるとき、複数の子の間ではどのように相続されるのでしょうか。
結論のみ述べると、単純な頭割りになります。つまり、子が1人であれば相続財産の2分の1を相続し、子が2人であれば相続財産の4分の1ずつを相続し、子が3人であれば相続財産の6分の1ずつを相続するといった具合になります。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分
かつての民法900条4号但書は、非嫡出子の法定相続分を非嫡出子の2分の1と定め、非嫡出子の相続分に対する差別的な取り扱いをしていました。しかし、ドイツでは1998年に、フランスでは2001年にそれぞれ非嫡出子の相続分に対する差別的取り扱いが撤廃されました。欧米諸国において非嫡出子の相続分に対する差別的取り扱いをする国は存在せず、日本はこの点に関し諸外国に遅れをとっていました。
このような世界情勢を受け、最高裁判所は、2013年9月4日、非嫡出子の相続分に対する差別的取り扱いを認めた民法900条4号但書は憲法14条1項の平等権に違反し無効であると判断したのです。ただし、最高裁判所は、それまでの最高裁判所が民法900条4号但書に対する合憲判断を繰り返していたこととの整合性を確保するため、「(その裁判で問題となった相続開始時点である)平成13年7月当時においては違憲無効であり、過去の最高裁判所の合憲判断を変更するものではない」との注意書きをしています。
そのため、①2001年(平成13年)年7月以降に相続が開始されたケースでは、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じであるとして事件処理がなされますが、②2001年6月以前に相続が開始されたケースでは、依然として、非嫡出子はその相続分に関して嫡出子の2分の1であるとの差別的取り扱いがなされる可能性があります。
ただし、③2001年7月以降に相続が開始されたケースであっても、最高裁判所の上記判断がなされる前に遺産分割協議や調停が成立していたり、審判が確定していたりするケースでは、そちらが優先されます。すなわち、遺産分割協議・調停・審判において、非嫡出子の相続分が差別的取り扱いを受けていたとしても、それらは法律上有効なものとして取り扱われることになります。
前妻との子の相続分
前妻との子も、被相続人・前妻との間の法律婚の男女関係で出生していますので、嫡出子です。
したがって、前妻との子であっても、他の子と全く同じように頭割りで計算した法定相続分となります。
現在の配偶者以外の者との子がいるとき
現在の配偶者との子が複数おり、それぞれが独立した家庭をもっていたとしても、通常は親戚づきあいがあるでしょうから、被相続人の死亡を知らないままであるということはないと思われます。
しかし、現在の配偶者以外の者との子がいるときは、現在の配偶者や現在の配偶者との子との親戚づきあいがないことが予想されます。すなわち、現在の配偶者以外の者との子は、被相続人の死亡を知らないままという事態が想定されるわけです。
法定相続人には遺留分というものが認められています。遺留分は法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人のときは、遺留分は法定相続分の3分の1)です。被相続人の遺言によって遺留分が侵害されたとき、侵害された法定相続人は遺留分侵害額請求権を行使し、自らの遺留分相当額に応じた金銭を請求することができます(この点について、従前の制度は「遺留分減殺請求権」といい、自らの遺留分に応じた相続財産を取得するものでしたが、法改正により、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続については、「遺留分侵害額請求権」といい遺留分相当額に応じた金銭請求しかできないこととされました。2019(令和元)年7月1日以前に開始した相続については、従前どおり「遺留分減殺請求権」を行使することとなります)。問題は、遺留分侵害額請求権の消滅時効は、「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年であるという点です。つまり、全ての法定相続人に対して被相続人の死亡の事実を知らせておかないと、相続開始の時から10年間である除斥期間が経過するまでは遺留分侵害額請求権の行使を受ける不安定な法的立場に置かれ続けることになります。
また、そもそも非嫡出子や前妻との子には一切の相続をさせない旨の遺言を被相続人が作成しておかなければ、法定相続人全員が参加する遺産分割協議が絶対に必要になります。遺産分割協議を成立させなければ、銀行口座から出金することも、不動産の登記名義を変更することもできません。相続財産は被相続人名義のまま凍結された状態が続くことになります(2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続については、一定額の預貯金を除く)。したがって、被相続人としては、死後に法定相続人間で無用な法的紛争を引き起こさないためにも、生前に遺言を作成した上で、財産を相続させる相続人に対し、自らの死後、直ちに自らの死亡の事実について、他の相続人に知らせるように指示しておくべきです。
心配なことがあれば弁護士相談を
現在の配偶者以外の者との子がいる方や、ご自分の父親にご自分の母親以外の者との子がいる方は、将来的に相続で法的紛争が生じるリスクがありますので、今のうちから将来を見据えた対処を準備しておく必要があります。
当事務所では初回相談は無料とさせていただいておりますので、相続関係でご心配な点やお困りの点がある方は、当事務所までご予約のお電話をいただければ幸いです。