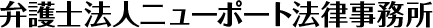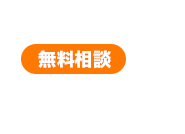遺言書が無効となるケース

せっかく遺言書を作成したにもかかわらず遺言者の死後に遺言が無効となってしまうと、全ての相続人が参加する遺産分割手続が開始することになり、各相続人は法定相続分に応じた相続財産しか相続することができなくなってしまいます。そこで、今回は、遺言書が無効となるケースについてご説明いたします。
公正証書遺言は無効になりにくい
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言、④危急時遺言の4種類があります。このうち、③秘密証書遺言と④危急時遺言はほぼ利用されません。世の中の遺言のほとんどは①自筆証書遺言と②公正証書遺言となります。②公正証書遺言は、公証役場に遺言者が赴き、公証人(通常は元裁判官や元検察官が公証人になります)が遺言者の本人確認をした後に遺言者の面前で全文を読み上げて内容を確認します。そして、これらの手続の全てを2人以上の証人(遺言の作成を弁護士に依頼したときは弁護士が証人の1人になります)が見守り、公正証書遺言に署名捺印します。しかも、一旦作成された公正証書遺言は公証役場でその原本が保管されますので、作成後の偽造・変造・破棄・隠匿のリスクがありません。公正証書遺言はこのような厳格な手続を踏んで作成されることから、基本的に無効になることはありませんし、その後も厳格に管理されることから、作成後に偽造・変造・破棄・隠匿されることはありません。
しかし、例外的に無効になるときもあります。公正証書遺言が無効となる場合として多いのは、遺言作成時に老人性の痴呆等で、遺言者に遺言能力(遺言を作成するのに十分な判断能力)がなかったという場合です。遺言者に十分な判断能力があるかどうかについては、もちろん公証人も確認しますが、ほとんどのケースでは公正証書遺言を作成する日に初めて会うだけですから、遺言者の老人性痴呆症の状態のいいタイミングであったりすると、公証人が気付かない可能性があります。
そこで、このような事態を避けるため、公正証書遺言を作成するときであっても弁護士に依頼すべきです。弁護士に依頼すると、遺言の中身をどうするかについて弁護士と打合せをすることになります。弁護士は、通常、打ち合わせの状況をメモしていますので、遺言者の死後、その遺言能力が問題になったとき、その遺言が遺言者の真意に基づくものであることについて、弁護士が極めて信用性の高い証人になることができます。
自筆証書遺言が無効になるケース①~自書
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、捺印しなければなりません。これらを1つでも欠くと無効になります。パソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりすると、それがほんの一部であっても無効になります。
では、代筆ではなく、手が震えて一人では字が書けないといった事情があるため、他人の手を添えて書かれた自筆証書遺言の効力はどうなるのでしょうか。この点について、最高裁判所昭和62年10月8日判決は、本来読み書きができた者が病気や事故等の原因により視力を失ったり手が震えたりするなどの理由で筆記について他人の補助を要することになったとしても自書能力は失われないとの判断を示しました。しかし、どこまでが代書であって、どこまでが介添えかの境目はあいまいです。遺言者の死後に遺言が無効になるリスクを避けるため、目が見えなくなったり手が震えて字が書けない状態になったりしたときは、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選択すべきです。
つぎに、カーボン紙を利用して複写された自筆証書遺言の効力ですが、この点について、最高裁判所平成5年10月19日判決は有効であると判断しましたが、あえてリスクを冒すべきではなかったといえるケースでした。最近ではタブレットにペンを使って手書き入力できる機能があります。それを利用して自筆証書遺言を作成したら確かに便利そうです。しかし、遺言者の死後に無効になるリスクがありますので、やるべきではありません。なお、氏名については、戸籍名だけではなく、本人との同一性を認識できる名(例えば、芸名、筆名、屋号、雅号)であっても有効です。しかし、遺言者の死後に無効となるリスクを避けるためには戸籍名を自署すべきです。
自筆証書遺言が無効になるケース②~押印
捺印する場所ですが、わが国の慣行では自署した氏名の名下に捺印しますので、氏名の名下に捺印すべきです。この点について、最高裁判所平成6年6月24日判決は、遺言書自体には捺印がなく、遺言書を封緘した封筒の封じ目部分に捺印されていた自筆証書遺言を有効であるとの判断を示しましたが、このような冒険をするメリットはありませんから、素直に氏名の名下に捺印するべきでしょう。また、捺印に使用すべき印章には制限がありませんので、認印でも三文判でも指印(指頭に墨や朱肉等を付けて押捺したもの)であっても有効です。しかし、遺言者の死後にその真意を巡って紛争が発生することを防止するためにも、氏名の名下には実印を押し、遺言書を封緘する封筒の中に印鑑証明書を入れておくべきです。
自筆証書遺言が無効になるケース③~日付
日付は特定の年月日を記載すべきです。「満60歳の誕生日」とか「還暦の日」との記載をしたとしても、遺言書作成の年月日を特定することができることから有効と解釈されていますが、日付の記載で独自色を出す意味がないため、素直に特定の年月日を記載すべきです。この日付は実際に遺言書を作成した日を記載しなければなりません。真実の作成日付でないときは、遺言は無効となります。また、年月の記載はあるものの日の記載がないときも、遺言は無効となります。さらに、日の記載に換えて「吉日」と記載しても、遺言は無効となります。
困ったら弁護士に相談を
このように自筆証書遺言は厳格な要式性が定められており、それを1つでも欠くと遺言自体が無効となります。遺言者の死後に遺言が無効となるリスクを避けるため、自筆証書遺言ではなく、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成することをお勧めします。