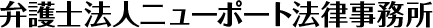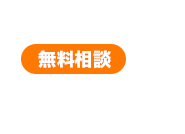事業承継に関する問題点

事業承継とは、被相続人が会社を経営している場合に、被相続人の生前に後継者を定め、被相続人の死後も円滑に会社が続いていくように準備をしておくことです。今回は事業承継に関する問題点についてご説明いたします。
事業承継の必要性
被相続人が会社を経営しているとき、自社株式や事業用資産を後継者に集中させることができなければ、後継者は円滑な会社経営をすることができなくなってしまいます。しかし、わが国においては、一般に、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式や事業用資産の割合が高いことから、遺言によってこれらを後継者(例えば長男)に全て相続させたとしても、他の相続人(例えば長女)によって遺留分侵害額請求権を行使されると、後継者はこれらを換価して遺留分侵害額の支払いにあてなければならなくなってしまいます。そのような事態にならないように、被相続人としては、遺言を作成しておくだけでは足りず、後継者に自社株式や事業用資産を集中させるための具体的な対策を生前に講じておく必要があります。
民法の制度を利用した事業承継について
民法の制度を利用した事業承継としては、①売買、②生前贈与、③遺贈、④死因贈与の各方法によることが考えられます。②③④には他の相続人の遺留分を侵害するときは遺留分侵害額請求権の行使を受けるリスクがあります。また、①の売買によっても、その対価が不当に安ければ、②③④と同様に遺留分侵害額請求権の行使を受けるリスクがあります。結局のところ、民法の制度を利用して事業承継をしようとすると、必ず遺留分の問題に直面することになります(なお、自社株式と事業用資産を後継者に集中的に相続させても他の相続人の遺留分を侵害しないときは、遺言や死因贈与によって後継者に相続させるだけで済みます)。
非後継者全員の協力が得られるとき
非後継者(例えば、被相続人の長男が後継者で、長女や次男が非後継者のときの長女や次男)の協力が得られる場合には、事業承継円滑化法の制度、すなわち、自社株式や持分に関しては除外特例制度、自社株式や持分以外の事業用資産については附帯特例制度を利用することができます。これらの制度によって、一定規模の特定中小企業に関し、3年以上の事業継続の実績があること、後継者が自社の議決権の過半数を有していること、後継者が代表者であることといった条件を満たせば、推定相続人全員の合意によって、後継者が被相続人から生前贈与された会社関連財産について遺留分を計算する基礎財産から除外することができます。なお、これらの制度を個人事業主は利用できませんので、農業や個人商店であったとしてもこれらの制度を利用するためには法人化するしかありません。
これらの制度によっても、後継者ではない相続人全員による合意が必要ですが、生存している被相続人による説得が可能となりますので、被相続人の死後に後継者たる相続人とそれ以外の相続人が事業用資産をめぐって対立するという事態を避けることができます。
なお、非後継者全員の合意が得られたときは、その1か月以内に経済産業大臣の確認を受け、更に経済産業大臣の確認から1か月以内に家庭裁判所に対して許可審判の申立てを行う必要があります。家庭裁判所は、これらの合意が非後継者全員の真意に基づくものであるかどうかを確認し、許可審判を出すことになります。経済産業大臣に対する確認申請や家庭裁判所に対する許可審判の申立ては後継者が単独で行うことができます。そのため、非後継者が自ら家庭裁判所に申し立てなければならない遺留分放棄の許可と比べると、非後継者を説得しやすく、円滑な事業承継を実現しやすいでしょう。
非後継者の中に反対者がいるとき
非後継者の中に除外特例や附帯特例に反対する者がいるときは、前項の各制度を利用することはできません。そこで、自社株式や持分について早い時期に評価額の固定合意をしておくことが考えられます。固定合意をすると、その後に会社が発展し、自社株式や持分の評価額が上昇したとしても、遺留分侵害額を算定する際の基礎財産は固定額が基準となり、固定合意後の値上がり益はそのまま後継者に取得させることができます。ただし、固定合意の金額は、弁護士・公認会計士・税理士等による証明書に基づくものでなければなりません。また、固定合意の対象は自社株式や持分に限定されます。事業用資産について固定合意をすることはできません。
後継者がいないとき
親族や従業員に適切な後継者がおらず、今後も後継者の育成の見込みがないときは、M&A(事業の売却)を考えることになります。今では様々なアドバイザー会社がありますので、それらに依頼してマッチング企業を探してもらい、条件が合う譲渡先が見つかれば、自身はお金をもらって事業から手を引くことになります。これに対し、条件が合う譲渡先が見つからないときは、徐々に事業を縮小していき、事業用資産についても処分し、従業員を解雇し、最終的には事業を閉鎖することになります。
困ったら弁護士に相談を
事業承継を成功させるためには、適切な後継者を育成することのほか、後継者ではない相続人の協力を得ることが極めて重要です。そのためには、子供たちが幼いうちから事業にかける自身の熱い思いを折に触れて話題にし、「誰が後継者になっても自社株式と事業用資産は後継者が全て取得することが当然である」という空気を形成しておくべきでしょう。
ただ、事業承継によって非後継者の遺留分を侵害するときは、法律の要求する厳格な手続を履践しなければなりません。弁護士に依頼するかどうかを検討するためにも、まずは法律相談を受けることをお勧めいたします。
当事務所では初回の法律相談料はいただいておりません。当事務所は皆様のお力になるべく最善を尽くすことをお約束いたします。皆様からのお電話をお待ちしております。